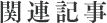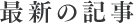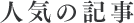ひな祭りの3月3日。桃を飾り、ひな人形を飾ったら、次はちらし寿司を片手に森に出かけて自然の音に耳をすましてみませんか? 実は3日3日「ひな祭り」は「耳の日」としても知られています。今日は、「聴く」ことを考えるおしゃべりです。
聴こえる音に、こだわらない。
電話の発明者であるベル氏(実は3月3日生まれ!)が、現代のスマホ社会を知ったらどんなに驚くでしょう。デジタル時代の昨今、より一層視覚に頼った暮らしのスタイルが増えているように思いますが、「耳の日」の今日は「聴く」ことに注目してみたいと思います。
はるか昔、哲学者のピタゴラスは「音楽は代替医療になる」と主張したと言われますが、実際に「音」は人に大きな影響を及ぼしています。ここで改めて話題にしたいのは、「聴こえない」音の効果。一般に人の耳がとらえられる音の周波数は20ヘルツから2万ヘルツと言われ、特に高い音は年齢とともに聴こえづらくなってしまいます。 これまで、「聴こえない音」は「不要な音」と考えられていて、たとえば音楽録音の際などは可聴域以外はカットされているのですが、ここ最近、「聴こえない音」が私たちの健康にかかわっていたという科学的な発見に、注目が集まっています。




取り入れたい、ハイパーソニック・サウンド。
それは、特に人には聞こえない超高周波の音域。脳科学者の大橋力氏がその効果に着目し、ハイパーソニック・サウンドと呼ばれています。ストレスを軽減したり、免疫力を向上したり、認知機能をアップするなどのさまざまな良い影響があると言われ、研究も日々進んでいるとか。ハイパーソニック・サウンドの主な音源は、豊かな自然の中で生息する多様な虫たちの声だと言います。もしかしたら、アフリカの熱帯雨林の中で生まれた人類の遺伝子には、この自然の音の記憶が刻まれているのかもしれませんね。
ひな祭りを、楽しもう。
そこで今年は、自然の音に包まれるひな祭りはいかがでしょうか? 新しい春の到来に、虫たちも歓迎の声を聴かせてくれている時期です。お供には、おすすめの「草花木果レシピ 春のちらし寿司」も、ぜひ。 ひな祭りと耳の日の3月3日をきっかけに、もっと健やかに、楽しい日々をお過ごしください。




<草花木果レシピ>春のちらし寿司のつくり方
【材料】2人分 *目安となります。 ご飯:1合 はまぐり:300g(殻つき)*砂抜きする 干し桜海老:8g エビ:中3尾 菜の花:3本 ホタテ:2個 *かにかまなどで代用も可! かぶ:中1/2個 しらすぼし:40g きぬさや:10本 甘夏(日向夏):適量 *なくてもOK すし酢:市販のもので米1合分の相当量 酒(純米酒):100cc 昆布:10g
【つくり方】 前夜の準備 <1>かぶの皮をむき、薄切りにして、30分くらい塩水につける。しなっとしてきたら、すし酢につける(2時間くらい)。 <2>菜の花を茹でて水気を絞る。食べやすいサイズにカットした刺身用のホタテと一緒に半日くらい(好みの味に) 昆布締めにする。味がととのったら食べやすいサイズにカットする。 <3>エビを茹でて薄く半分に切る。 <4>鍋にはまぐり、酒、昆布を入れ酒蒸しに。はまぐりの口が開いたら、火を止め、取り出して身を外す。 <5>はまぐりの酒蒸しで余った出汁の熱さがとれたら、<4>のはまぐりと<3>のエビを浸す。さらに干し桜海老を加え、 そのまま数時間置く。朝まで(半日)そのまま冷蔵庫に入れて保管してもOK。
朝の準備 <6>炊きたてのご飯にすし酢を混ぜて放置して冷ます。 <7>きぬさやの筋をとって茹でる。 <8>しらすぼしをご飯にまぜる。 <9>前夜に用意した<1>カブ、<2>菜の花とホタテ、<5>エビ、はまぐりと干し桜海老を出汁から取り出し軽く水気をとって、 のせる。最後に<7>のきぬさやと、剥いて小さくカットした甘夏を散らしたら完成! ピクニックに持参しても色はきれいなままで、美味しくいただけます。